~カレ目線~
【病室】
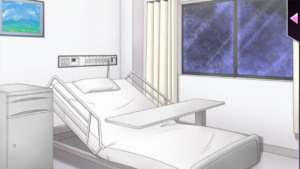
うっすらと目を開けると、見知らぬ天井が目に入った。
(あれ···ここ···)
後藤
「気が付いたか、歩」

(え···)
東雲
「後藤···さん···?」
「オレ···なんでここに···」

後藤
「覚えてないのか?『コチ電業』で倒れただろう」
(そうだ···)
(アジトから助け出された後、無理を言って立ち寄ってもらって···)
東雲
「メモリ···」
後藤
「大丈夫だ。石神さんと氷川に託してきた」
「それで良かったんだろう?」

東雲
「はい···」
オレが石神さんに渡す予定だったデータは、すでに破棄されてしまっていた。
残りは「万が一」に備えて作っておいた、あのコピーのみだ。
後藤
「心配するな。2人が必ず何とかしてくれる」
「お前はゆっくり休め」
東雲
「···はい···」

再びまぶたが重たくなってくる。
現実からうつつに落ちる狭間で、オレは今回のことを思い返していた。
【ラーメン屋台】

事の起こりは、大手電機メーカーを襲ったサイバー攻撃事件だった。
そのことで余計な手出しをしたオレは、警視庁に通うハメになり···
難波
「お疲れさん。いろいろ大変だったな」
「だいたいのことは聞いたか?」

東雲
「はい···でも、まだ信じられません」
「父の会社が、過激派組織と接触してるかもしれないなんて」
難波
「···そんな顔するな」
「お前の両親が関係していると決まったわけじゃない」
「単に関係者が社員として潜り込んでるだけかもしれん」
「···で?上層部はなんて?」
東雲
「今日は、特には···」
「でも、たぶん···」

難波
「潜入捜査、か?」
東雲
「······」
難波
「身内にやらせるとはエグいことを考えるな」
「本来なら御法度のはずだが···」

東雲
「使える駒としてはオレが最適ですから」
「もちろん信用してもらえれば···ですが」
その話が正式にオレにおりていたのは翌日のことだった。
【警視庁】

今回、捜査にあたるのは加賀班ではなく別班の連中だった。
なので、オレが指示を仰ぐのはその班の班長ということにある。
最初の会議のとき、オレは1点だけ彼に要望を出した。
班長
「···氷川サトコ?」
東雲
「オレの補佐官です」
「潜入中に補佐役が必要になったら、彼女にお願いしたいのですが」

班長
「は?バカか、お前は」
「お前の補佐官ということは、まだ訓練生だろう」
東雲
「そうです。ですが彼女は···」
班長
「訓練生なんて言語道断だ」
「補佐役が欲しいなら、うちの班から連れて行け、いいな?」
東雲
「···分かりました。考えておきます」
(使えるヤツがいるなら···だけど)
これが通常の捜査なら、もちろんこんなことは思わない。
現場経験を積んでいる刑事の方が、訓練生よりよほど使えるだろう。
けれども、今回は勝手が違う。
「東雲歩」として潜入する以上、どこまで自由に動けるのか分からない。
だからこそ、少ない指示で手足となってくれる人間が欲しいのだ。
【東雲 マンション】

状況が変わったのは、木曜の夜中のことだった。
彼女をタクシーに乗せて帰らせたあと、室長から連絡が来たのだ。
難波
『例の案件だがな、ひとまず加賀班が受け持つことになった』
東雲
「本当ですか?」

難波
『ああ。ってことだから···』
『来週からすぐに潜入捜査に行ってくれ』
東雲
「!」
難波
『じゃあ、詳しいことはまた明日···』
東雲
「待ってください。学校はどうするんですか?」
難波
『ん?公安学校のことか?』
『それなら異動になると···』
東雲
「それは聞きました。今回の潜入は長期に渡る可能性があるからって···」
「でも、引継ぎはどうするんですか?今週はもう明日しかないのに···」

難波
『あーそうだなぁ』
『ま、何とかなるだろ。後任は黒澤だし』
『それじゃ』
東雲
「ちょ···待ってください!室長···」
(そんな、いきなり···)
(しかも、よりによってこのタイミングで···)

つい数時間前、うちの補佐官をきつく咎めたばかりだった。
そのこともあって、オレ自身、迷いが生じ始めていた。
(今日みたいな様子なら、補佐役なんて任せられない···)
けれど、信じてみたい気持ちもあった。
それに、補佐役には万が一のときの「鍵」を渡しておきたい。
(オレが指示を出せない状況に立たされても、何とかなるように···)
迷いに迷った末、オレは内緒でその「鍵」を彼女に送ることにした。
それを使わなくても済むように、ひそかに祈りながら。
【コチ電業】
翌週。
オレは、予定通り「コチ電業」に入社した。
最初に着手したのはシステム管理部絡みの仕事だ。
表向きは「サイバー攻撃」の対策・改善をするため。
けれども、本当の目的は社内から外部へのアクセス確認をすることだ。
その結果、浮上したのが···
【役員室】
櫻井
「社長補佐、お茶をどうぞ」

東雲
「ありがとう」
(秘書課の櫻井修子···元SE···)
社外秘データへの数度に渡るアクセス。
さらに、外部サイトへアクセスする際の不自然な経由の仕方。
(奇妙なことだらけなんだよね、彼女···)
(おまけに···)
櫻井
「そういえば、Aホテルのバーをご存知ですか?」
「今後、社外の人間との取引に使えそうなお店ですが···」
東雲
「いや、行ったことないけど、いい店?」

櫻井
「ええ、とても」
「よろしければ、いつでも案内いたしますわ」
「もちろん、勤務時間外でも」
どこか艶っぽさを漂わせた微笑みに、ひとまず「考えておくよ」と返しておく。
(ほんと、セオリー通りすぎ···)
(こうもあからさまに接触してくるなんて···)
接触回数が増えれば増えるほど、彼女の目的を探りやすくなる。
その一方で、オレ自身の行動が制限されてしまうのは否めない。
(やっぱり補佐役を1人入れてもらわないと···)
(櫻井修子が、次の行動に出る前に···)

【ラーメン屋台】
その日の夜。
難波
「氷川を補佐役に?」
加賀
「ガキが···何を考えてやがる」

東雲
「何って、任務遂行のことだけですよ」
「彼女なら適任なんです。先日、コチ電業の捜査に当たったときも···」
東雲
「氷川さーん、糖分ー」

サトコ
「缶コーヒーでいいですか?」
東雲
「うん」
「あと、ここの資料だけど···」
サトコ
「揃えておきました。どうぞ」
東雲
「······」
サトコ
「??違いましたか?」
東雲
「···いや」
難波
「···なるほど、言葉にしなくても···か」
東雲
「そうです」
「それに、そろそろまた大きな経験を積ませてもいいと思いますけど」

加賀
「なにが『経験』だ。テメェはもう教官じゃねぇだろうが」
東雲
「それは···」
加賀
「補佐役なら他のヤツにやらせる」
「女がいいなら、俺が抱えてる連中から見繕って···」
難波
「いや、氷川もありだろ」
「歩の意図を汲み取れるって点では」

東雲
「じゃあ···」
難波
「ただし、最初はお試しからだなー」
「前回の殿井建設への潜入捜査より今回の方が難易度が高いし」
「で『お試し』で問題なさそうなら正式な任務内容を伝える···」
「それでどうだ?」
東雲
「···分かりました」

室長が提案した「お試しテスト」は2段階に分かれていた。
1段階目は、兵吾さんの補佐官となってチェックを受けること。
そして2段階目は···
【コチ電業 エレベーター】
東雲
「どうしてうちの会社にいるの?」
「誰の命令?」

サトコ
「······」
東雲
「答えなよ。新人アルバイトの『長野』さん」
わざと耳元で囁くと、彼女は背筋をぴくりと強張らせた。
まぁ、当然だ。
彼女にとって、オレは「元担当教官」で「恋人」で···
(今は「部外者」なわけなんだけど···)
(さて、どう出る?)
どうするべきなのかは、これまで教えてきたはずだ。
(ほら、頑張って···)
(ちゃんとクリアしなよ)

果たして、彼女は「答え」を間違えることなくエレベーターを出ていった。
そのあと、櫻井修子に小言を言われていたのは気の毒だったけど。
【ラーメン屋台】
翌日の夜。
颯馬
「お久しぶりです。どうですか、新しい潜入先は」

東雲
「まぁ、それなりに」
「じゃあ、まずはオレの報告から···」
その日の報告事項と室長への伝言を、颯馬さんに簡潔に伝える。
東雲
「···以上です。詳細はこのメディアに」

颯馬
「確かに受け取りました」
「では、こちらからも」
「加賀さんが、例の過激派組織のアジトを突き止めました」
「近いうちに協力者を使って、中の様子を探らせるそうです」
東雲
「分かりました」
颯馬
「それと、室長からの伝言ですが···」
「貴女の元補佐官に、正式に任務を任せることが決まりました」
「今日この後、今回の任務内容を彼女に伝えます」
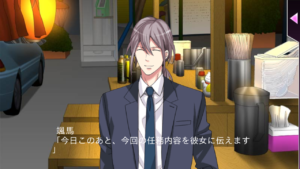
東雲
「そうですか。じゃあ···」
(これで、ようやくあの子にすべてを···)
颯馬
「ただし、条件がありまして」
「まず、彼女を潜入させるのは1ヶ月以内にすること」
「これは訓練生なので当然ですね」
東雲
「···分かりました」

颯馬
「そしてもう1つ」
「貴方が潜入捜査で入っていることは、彼女には伝えません」
東雲
「···っ」
「どういうことですか!」
颯馬
「万が一のときのための対策ですよ」
「彼女が過激派組織に捕まったとき、余計なことを···」
「つまり、貴方が潜入していることを喋らないように」
東雲
「······」
颯馬
「貴方からの指示は、私や石神さん経由で伝えます」
「なにかご要望はありますか?」
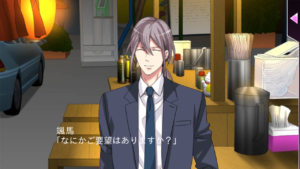
(ご要望って···)
(なるほど、反論は受け付けないってわけか)
今回の指示は、もしかしたら上層部からのものなのかもしれない。
それなら室長に掛け合ったところで、これ以上どうにもならないだろう。
(ま、補佐役で認められただけマシか···)
それに、考えようによってはいいチャンスかもしれない。
今回の任務を1人で果せたら、彼女にとっては大きな自信になるはずだ。
東雲
「じゃあ、氷川さんにこれを」

オレは、ポケットから小型の盗聴器を取り出した。
本当なら、機会を見て自分で取りつけようと考えていたものだ。
颯馬
「場所は?」
東雲
「櫻井修子のデスク周辺に」
「期間は明日中」
「秘書課は外部研修で直帰の予定なので」
颯馬
「分かりました。伝えておきましょう」
「この事件は、貴方から彼女への置き土産でもあるでしょうから」
(置き土産···か)

確かに、オレははもう公安学校の教官じゃない。
訓練生としての彼女にできることはそう多くはないのだ。
(だったら、少しでも彼女が成長できるように)
(あの子のまっとうな正義感が、きちんと実を結ぶように)
それからは自分の任務をこなしつつ、彼女を見守るのがオレの日課になった。
ときに危ない状況を助けたこともあった。
一方で、任務とは関係のないくだらない嫉妬に駆られたこともあった。
でも、だからこそ気付けたのかもしれない。
「本当の黒幕」の存在に。

最初のきっかけは視線だった。
(···ん?)
(誰かに見られてる?)
東雲
「!」

(あの男、広報課の···)
見覚えがある、なんてものじゃなかった。
なにせ、うちの補佐官が社内で一番親しくしている相手だ。
(まさか、バレたとか?オレと彼女のこと···)
だが、彼女と2人きりになったのは2度だけ···
密室ともいえるエレベーターの中と、秘書課に忍び込んだ時だけだ。
(それだけでバレるはずがない···)
(だとしたら気のせいか?)

けれども···
東雲
「···っ」
(また視線?)
東雲
「!」

(···なんなんだ、いったい)
そうしたことが何度か続き、オレは彼を無視できなくなった。
【役員室】

そこで、人事部のDBで彼の経歴を確認することにしたのだ。
(加地寛人・広報課所属···)
東雲
「ふーん···」

(うちの会社に来る前は、けっこう転々としていたんだな···)
(ナツカ珈琲店···サイキ・エレクトロニクス···)
(とよおか出版···JPEL···)
東雲
「···ん?」
(JPELとサイキ・エレクトロニクスにもいたんだ···)
ただの偶然か、それとも···
そう考えた一番の理由は、最近の捜査に違和感を覚え始めていたからだ。
(証拠だけを見れば、櫻井修子が関係者のはず)
(けど、なにか違う気がする···)

彼女とは別に黒幕がいる···
あるいは、櫻井修子は利用されただけでまったくの無関係だった···
そんな可能性が、どうしても頭から拭えないのだ。
(さて、どうするか)
幸い、うちの補佐官はやるべきことを頑張ってこなしている。
(だったら、櫻井修子の捜査はこのまま彼女に任せていいかもしれない)
(オレはオレで、別角度から洗い直してみても···)
(たとえば、この男を探ってみるとか···)

結果としてはこれがビンゴで、オレが捕まるハメになったのだけど。
【病室】
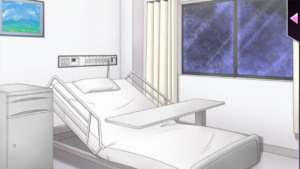
???
「では、こちらで入院の手続きをお願いします」
???
「分かりました」
(この声···父さん···?)
再び、オレは薄く目を開けて、声の聞こえた方に顔を向ける。
ちょうど父さんと看護師が、病室を出て行くところだった。
(そっか、入院···)
(まぁ、アジトではえらい目にあったし···)
その2人と入れ違いで、後藤さんが病室に入ってきた。
後藤
「歩、起きてたのか!?具合は?」

東雲
「さっきよりはマシです···」
後藤
「···そうか」
後藤さんは息を吐くと、素早く周囲に視線を走らせた。
そして、誰もいないことを確認して、ようやく口元に笑みを浮かべた。
後藤
「さっき、石神さんから連絡が入った」
「例のパスワードは、無事に解けたそうだ」
東雲
「それって···」

後藤
「もちろん、解いたのは氷川だ」
「今、こっちに向かっているらしいぞ」
東雲
「そう···ですか···」
万が一のため「鍵」として、潜入前に送ったメールだった。
忘れないようにインパクトを考慮して···
さらに画像を覚えるのが得意な彼女だったから、文字列を顔文字にして···
(よかった···思い出してくれて···)
後藤
「満足そうな顔をしているな」
東雲
「!」
後藤
「氷川が、期待以上の働きをしたからか?」

東雲
「そういうわけじゃ···」
「まだ過激派組織の目論見を阻止したわけではないですし」
「その糸口を手に入れただけで」
後藤
「······」
東雲
「でも、そうですね···」
「正直ホッとしています」
後藤
「担当教官としてか?」
東雲
「『元担当教官』としてです」
「できれば、もう少し···育ててみたかったですけど···」

ぽろりとこぼれた本音に、後藤さんは「本気か?」と苦笑した。
後藤
「それなら室長にかけあってやるぞ」
「『歩が教官に戻りたがっている』と」
東雲
「それは無理でしょう。もう透がいますし」
後藤
「だが、アイツは自由人すぎるからな···教官には向かない···」
【東雲 マンション】

そして···
東雲
「······」

サトコ
「···なんですか、じっと見て」
東雲
「べつに」
オレの答えに、彼女は首をひねりつつも、再びテキストに向き直る。
そう、せっかくの休日だというのに、うちの彼女は勉強中なのだ。
(ま、仕方ないか)
(1ヶ月も学校を休んでたわけだし)
もちろん、オレも山のように教官としての業務が溜まっている。
(やっぱ、面倒くさ···)
(教官なんてオレの柄じゃないし)
(我慢することも何かと多くて···)

そこまで考えたところで、オレはある事実に気が付いた。
東雲
「···あのさ」
「キミ、オレが教官に戻ってよかったって思ってる?」

サトコ
「もちろん思ってますけど···」
東雲
「本当に?」
「またパシリにされても?」
サトコ
「!」
東雲
「エビフライを勝手に食べられても」
サトコ
「そ、そのあたりは、いちおう対策を練ってますんで」
東雲
「ふーん、そう···」
「でもさ」
「もし、オレが公安学校に戻らなかったら···」
「キス以上のこと、できたかもよ」

サトコ
「ゲホッ!」
東雲
「教官と教え子じゃなくなるわけだし」
「それなら別に···」
からかい半分で訊ねるオレを、彼女は真っ赤になって睨みつけた。
サトコ
「そ、それは卒業後の楽しみにしてますんで!」
東雲
「······」

サトコ
「そういうのも、その···あれですけど···」
「今は、まだ教官に教わりたいことがいっぱいあるっていうか···」
「現場に出ればそんなヒマはないって、今回痛感しましたから」
東雲
「······」
サトコ
「だから、教官がまだ学校に戻ってきてくれて嬉しいです」
東雲
「···あっそう」
少し拍子抜けしつつも「悪くない」と思っている自分がいる。
だって、オレだって興味がある。
この子がどんなふうに成長していくのか。
どんなことを学び、どんな志を抱くようになるのか。
それを見守ることができるのは、担当教官ならではの楽しみな気がするのだ。
(だったら、いっか···卒業まで待っても···)
サトコ
「あ、でも···!」
ハッと顔を上げた彼女は、急に赤くなってうつむいてしまう。
東雲
「なに?」

サトコ
「え、えっと、その···」
「なんていうか···」
東雲
「···だから何?」
サトコ
「キ···」
「キスはいつでも大歓迎···です!」
東雲
「······」

サトコ
「だって、そこは撤回···でしたよね?」
東雲
「······」
「···キモ」
「モジモジしすぎ」
サトコ
「だ、だって···!」
抗議しようとした彼女を、背中から抱きしめる。
髪をかき分けて首筋を吸い上げると、驚いたように肩が跳ねた。
サトコ
「教官···それっ···」
東雲
「······」

サトコ
「ダメです。痕、残って···」
「···っ」
徐々に熱を帯びる首筋から、甘い香りが漂ってくる。
香水とは違う、彼女独特の香り···
(たぶん、オレしか気付いていない···)
サトコ
「教官···っ」
(ヤバ···)
(本当の意味で、全部撤回したくなってきた···)
(この間は、なんとかギリギリ誤魔化したのに···)

白い肌に赤い痕を残しながら···
そんな不埒なことを考えているのは、教官でいる限り絶対に秘密なのだ。
Happy End
